※本ページにはアフィリエイト広告が含まれています。
「私はこのプロジェクトには最初から反対だったんだ!」
最初は味方だったはずの人が、状況が変わった途端に態度を一変させる。
「実は前から応援していたんだよねー」
自分を非難ばかりしていた人が、態度を変える。
どちらも「手のひら返し」と呼ばれる行動です。ネットでは「手のひらクルー」などと呼ばれることもあります。
わかりやすい例
2022年のサッカーワールドカップでの日本代表に対する評価。
大会前は「どうせ無理」と、冷ややかな目で見ていた人たちが、日本代表が勝ち始めた途端、
「やっぱり日本は強い!」「監督は名将だ!」と持ち上げ始めました。
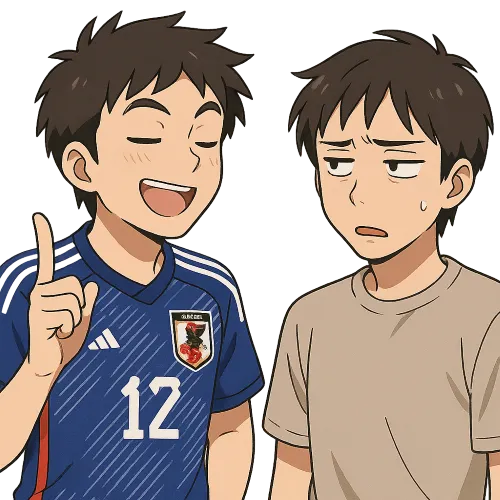
しかしこれがスポーツ観戦の場ならばまだしも、自分の職場で、しかも自分のキャリアに直結する場面で起きたら、たまったものではありません。
今回の記事では、手のひら返しをする人の心理を分析しつつ、それによる被害を最小限にする方法を考えてみました。
今回の記事はこんな方におすすめ
- 手のひら返しをする人を見分けるポイントを知りたい
- 手のひら返しをする人の心理を知りたい
- 手のひら返しにどんなパターンがあるのかを知りたい
- 他人の手のひら返しによるダメージを回避したい
- 歴史上、有名な手のひら返しについて知りたい
「手のひら返し」される側の心理
言うまでもなく「手のひら返し」をされた側の人は深く傷つきます。
「この人のことは信用できない」
「この人の言うことは次からは真に受けないようにしよう」
「もう利用されるのは御免だ」
と、警戒モードに入ります。
しかし、影響はそれだけではありません。
チーム全体への影響
さらに深刻なのは、こうした手のひら返しが一度発生すると、チーム全体の士気が一気に低下することです。
「あの人は成功してるときは褒めるけど、失敗するとすぐ切り捨てる」
と周囲が感じれば、メンバー同士の信頼関係は壊れ、協力しようという気持ちが失われていきます。
実務面での非効率
さらに実務面でも影響は馬鹿にできません。
プロジェクトが何かにつまづいた途端に上司が「やっぱりこのプロジェクトはダメ」と態度を変えると、それまでの作業が無駄になってしまいます。
プロジェクト自体が中止になった場合はもちろん、軌道修正の場合でもやり直しの手間が発生し、時間のロスとなります。
「手のひら返し」する側の心理
では、「手のひら返し」をする側の心理はどうでしょうか?
ここでは一方的に悪者と決めるのではなく、様々な場合について考えてみます。「する側の心理」を把握しておくことが、被害を防ぐための第一歩とも言えるからです。
なお、私の主観に基づきますが、各タイプごとに「悪質度」という概念を設けてみました。数字が大きくなるほど悪質だと思ってください。
悪質度0.5:内心の不満が限界を超えたケース
それまで、少なくとも表面的には協力的だった人が急に態度を変えると
「裏切られた!」
と感じるのが普通です。
しかし態度を変えた人の内心では、以前から貯めていた不満や不信感が限界を超えて爆発した可能性もあります。
「手のひらを返された」側の人からすると自分こそ被害者ですが、相手側からするとそうではないかもしれません。つまり、お互いに自分こそが被害を受けた側だと思っているケースです。
悪質度1:本人の意思ではなく外的圧力の結果
ときには本人の意志ではなく、上司や取引先など外部の圧力によって態度を変えざるを得ない場合もあります。
たとえば、取引先の担当者が急に冷たくなった場合
「今後、この事業は縮小するから」
という指示が上司から出ていた、ということもあり得ます。
この場合、窓口となっている担当者を責めることに意味はありません。再度アプローチを図るにしても、そうなった背景を考えることが重要です。
悪質度2:優柔不断で流されやすいタイプ
相手が周囲の意見や状況に流されるタイプだった場合です。
彼らは自分の中に確固たる判断基準がなく、周囲の意見に流されて態度を変えます。
これは行動経済学で言うところの「社会的証明」の影響で
「みんながそう言っているから、こっちにした方が良いのかも」
と思い込んでしまう心理バイアスが働いています。
なお、手のひら返しをされた側からすると
「あの人は優柔不断だ」
となりますが、結果的にその案件が上手くいったのであれば
「あの人が臨機応変な判断をしてくれて良かった」
という判断もできます。
また、状況の変化に対応して方針を変更した場合については、後から触れます。
悪質度3:保身・自己防衛のために意図的に行っているタイプ
ここからは悪質度が一気に高くなるパターンです。
まず自分の立場を守るために意図的に手のひら返しを行う人です。
- 上司や経営陣に認められたい(承認欲求)
- 強い側、有利な側につきたい
- 部下や同僚に嫌われても「評価」「昇進」「収入」のほうが大事(優先順位の問題)
このような人は、ダブルスタンダード(場面ごとに自分に有利な基準を使う)を自然に使います。
彼らにとっては、倫理よりも損得勘定が優先です。
こういった相手への対策は、後ほどまとめます。
悪質度4:自己奉仕バイアスによる認知の歪み
心理学では、人間が自分にとって都合よく物事を解釈する傾向を「自己奉仕バイアス」と呼びます。
- 成功したとき:「自分がアドバイスしたおかげだ」
- 失敗したとき:「部下の能力不足だ」
注意すべき点は、気持ちを切り替えるためにそのように考えようと努力しているのではなく、本人は本気でそう思っているという点です。つまり本人には悪意はありませんが、逆にその分より悪質だと言えます。
このバイアスが強い人ほど、状況が悪化した途端に責任転嫁のための手のひら返しが起きやすくなります。
悪質度5:さらに過剰な自己防衛本能が働くケース
他人から見ると、明らかに手のひら返しをしているのですが
「私は最初からこう主張していた!」
と本気で言い張るタイプです。
この場合も「本気で」という点が重要で、本人の中では記憶の改ざんが起こっています。
虚言癖(きょげんへき)のある人には、嘘をつくだけでなく、自分がついた嘘と現実の区別がつかなくなる人がいますが、このタイプはそれに近いと言えます。
つまり自分の過去の発言や態度の記憶すら都合よく書き換え、心の安定を保とうとしています。もはや単なる責任転嫁ではなく、本人の中で現実の認識(認知)が歪んでしまっているという酷い状態です。
「手のひら返し」されないための対策
ここまで書いたように「手のひら返し」をする人の中では、様々な心のメカニズムが働いています。
これに対して、こちらから働きかけることで相手に変わってもらうことを期待するのは、多くの場合で徒労に終わります。それよりも、まずは自分で自分を守る行動を取る方が現実的です。
ここでは、職場での「手のひら返し」から自分を守るための実践的な対策を解説していきます。
手のひら返しする人を見分ける
まずは、こんな特徴が見られたら要注意です。
- 会話の中で、過去の発言と矛盾していることが多い
- 指摘されると「そんなこと言ってない」「覚えてない」と平然とはぐらかす
- 責任が発生する場面では逃げ腰になるが、成果が出たときだけ前面に出てくる
- 上司や周囲の評価に異常に敏感で、それに応じて態度を変える
つまり、自分の発言や立場に対する責任感が希薄なタイプは、手のひら返し予備軍と考えてよいでしょう。
距離を取る・関わりを最小限にする
「この人、危ない」と思ったら、深く関わらないことが鉄則です。
- 必要以上に親しくなりすぎない
- 重要な判断や責任が発生する場面では、その人に依存しない
- 情報共有は最小限、かつ必要な範囲に絞る
これは自分を守るための健全な境界線の設定です。
やり取りを記録に残す・周囲と情報共有する
これは定番、かつ有効な対策です。
- メールやチャットでのやり取りは必ず記録に残し、チームメンバーをCCに入れるなど共有
- 口頭のやり取りは後で「○○の件、さきほどお話しした通りで進めますね」と文章でフォローする
- 打ち合わせの議事録を共有し、第三者の証人を作る
さらに効果的なのは、「情報がきちんと周囲に共有されている」という事実を本人にも分かる形で伝えておくことです。
例:折を見て会議の場で「この件については○○課長からもフォローを頂いています」等の発言をする。
⇒「後から手のひら返しはできない」という心理的プレッシャーになる。
こういった対策により「言った・言わない」の不毛な議論をせずに済みます。
背景を推測する
万が一、手のひら返しをされたとしても、単純に「この人は裏切った」と思い込むのは早計かもしれません。
- 本人の意図とは限らない
- 背後に上司や取引先など、外部の力が働いている可能性もある
- 社内の力関係や市況の変化があったかもしれない
背景を冷静に分析することで、人間不信など感情面で不要に傷付かずに済み、次の一手を考えやすくなります。
手のひら返しが最善の判断である場合
ここまで「手のひら返し」のネガティブな側面を中心に見てきました。しかし、すべての手のひら返しが悪いわけではありません。
むしろ、状況の変化に応じて柔軟に意見や行動を変えることは、合理的で賢い選択である場合もあります。
状況の変化への柔軟な対応
ビジネス環境は、常に変化しています。
たとえば、
- 自然災害や疫病、戦争の発生
- 原材料の高騰
- 市場のトレンドが急激に変わった
- 顧客のニーズが想定と大きくズレた
- 技術や法規制が変わった
- 社内の方針やリソースが変更された
こうした状況では、むしろ最初に立てた計画や意見に固執することの方がリスクです。
柔軟に意見を変えるのは、責任回避ではなく「現実への適応」であり、場合によってはチームや組織を守るための賢明な判断と言えます。
必要な方針変更と「手のひら返し」の違い
とはいえ合理的な理由による方針変更であっても、その理由が伝わっていない人からすると「手のひら返し」と同じです。つまり「変更の理由がきちんと伝わっているのか」がポイントです。
- 予め、状況次第では途中で方針の可能性が有ることを伝えておく
- 変更した場合は理由をきちんと説明する
経営陣や役職者の立場からすると、たとえ適切な判断であっても伝達が不十分だと、社内の士気低下を招く可能性が有ることに注意する必要があります。
歴史上の出来事で見る「手のひら返し」
ここでは歴史上に登場した「手のひら返し」を振り返りつつ、そこに潜む心理や集団のメカニズムを読み解いていきます。
太平洋戦争の終戦前後、日本のマスコミの手のひら返し
戦前~終戦まで、日本の新聞などは
「戦争は正義だ」
「国のために戦うべき」
と一斉に煽っていました。
ところが終戦が決まった途端に、
「平和こそ正義」
「戦争は悪だった」
と、一気に論調を転換。まさに日本の歴史に残る大規模な手のひら返しです。
産褥熱と医療界の手のひら返し
19世紀、医師ゼンメルワイスが
「産褥熱の原因は医師の手の不衛生であり、手洗いが重要」
と提唱しました。
しかし当時はまだ細菌の存在が分かっておらず、医療界はこれを激しく非難。結果、ゼンメルワイスは医学界から排除され、悲惨な最期を迎えます。
ところが、彼の死後しばらくしてから細菌学の発展により、「手洗いこそが感染予防のカギ」であることが証明され、医学界は一転してその重要性を強調しました。
反発 ⇒ 支持への180度の手のひら返しです。ゼンメルワイスは生前は不遇でしたが、現在では感染症予防の基礎を築いたものとして高く評価されています。
集団心理と集団浅慮の影響
これらの事例の背景には、心理学でいう「集団浅慮(しゅうだんせんりょ)」という現象があります。
- 集団の中で対立を避けたい
- 空気を読むことで安心感を得る
- 「みんながそう言っているなら間違いない」と思い込む
こうした心理が働くことで、正しいかどうかよりも「多数派に乗ること」が優先され、一つの方向に集団全体で動くことになります。
メディアと世論の偏向も、手のひら返しを助長
こうした、
1つの方向に世論が一斉に流れる ⇒ 手のひら返しの後、反対方向に動く
という一連の動きを助長するのがマスコミなどメディアです。
- ある出来事が話題になるとセンセーショナルに報道
- 報道されていた内容とは逆の結果(例:サッカー日本代表の活躍)が出ると、何事もなかったように逆方向に煽る
現代ではマスメディア以外にもSNS等で情報を調べる方法もあります。複数の見方があるはずの出来事なのに、1つの側面ばかりが取り上げられる場合は、特に注意してチェックすることが必要です。
まとめ|手のひら返しから自分を守るために
「手のひら返し」は誰の周りにも起こり得る現象で、その背景には心理学的な仕組みや外部からの圧力が存在します。
自分が被害を受けないようにするうえで、最も重要なのは
「相手が変わることを期待せず、自分を守る行動を取ること」です。
- やり取りは必ず記録に残す
- 周囲と情報を共有し、孤立しない
- 手のひら返ししやすい人とは適切な距離感を保つ
また、自分が意見を変える立場になった場合でも、「なぜ変えたのか」を丁寧に説明することが周囲からの信頼を維持するための鍵です。
変化に柔軟であることと、説明責任を果たすことは両立可能です。自分の身を守りつつ、誠実なコミュニケーションを心がけましょう。
【転職を検討中の方におすすめの記事】
よくある質問&疑問(FAQ)
本記事を最後までご覧頂き、誠にありがとうございます。
内容に関して、想定される疑問点およびその対処法についてFAQ形式でまとめました。



コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 手のひら返し|する側・される側それぞれの心理と自分の守り方 […]