※本ページにはアフィリエイト広告が含まれていますが、記事内容は公平さを心がけています。
「あの課長とこれからも一緒に仕事なんて絶対ムリ…」
「今の仕事、辞めたほうがいいのかな」
「でも、本当に転職してうまくいくのか…?」
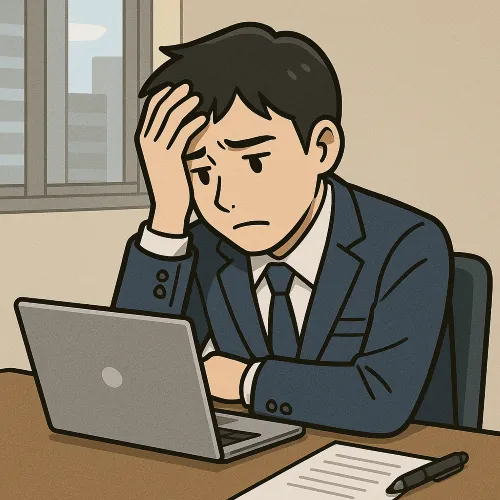
そうして思考が堂々巡りした挙句、
「なぜ自分はこんなに決断できないのか」
と自分を責めてしまい、自己肯定感の低下まで招いてしまってはいないでしょうか?
この記事は決断できないことを責めるのではなく、判断を下すことに必要以上に慎重になったり、先延ばしにしてしまう人間の心理について、そのメカニズムを解説します。
今回の記事はこんな方におすすめ
- 転職しようか迷っている
- 転職すべきと思っているのに先延ばしにしている
- 転職を迷ってばかりで、決断ができない自分を嫌いになりそう
- 本当に転職すべきかどうか、自分の頭の中を整理したい
転職に迷ってしまうのは「自然な心の動き」
結論から書いてしまうと、人間の脳(心)は変化を拒み、現状維持を好むような本能が備わっています。
このような心理的傾向は「現状維持バイアス」と呼ばれます。
なお変化を嫌うのは個人レベルの判断に限ったことではありません。
例えば、「今まではこのやり方で上手くやってきたから」…と、過去の成功事例にこだわるあまり経営が傾いてしまった老舗企業の例など、皆さんもニュースで見かけたことがあるのではないでしょうか?

コダック:過去の栄光に縛られた企業
よく取り上げられるのが、デジタルカメラの時代に乗り遅れたフィルムメーカー、コダックの例です。
ちなみにコダックは世界初のデジタルカメラを1975年(!)に開発していたのにも関わらず、フィルム事業への影響を気にするあまり、本格参入が遅れてしまったことが凋落の原因となりました。
転職を考えている人の心の中で現状維持バイアスが働くと、
「新しい職場にうまく馴染めなかったらどうしよう」
「今より悪くなったら?」
今の仕事に不満があるのにも関わらず、リスクの方ばかりに意識が向いてしまいます。
さらに、転職に迷う心理には「損失回避バイアス」も関係しています。
これは、人は「得られる利益」よりも「失う可能性のあるもの」に対して強く反応してしまうという心理です。
つまり、
- 今の職場に残ることで得られる安心感
- 転職によって失うかもしれない人間関係や収入、評価
これを心の中で天秤にかけたとき、
転職すべき理由 < やめない方が良い理由
…のように感じられてしまうのです。
自己分析①:あなたがしたいのは「退職」?それとも「転職」?
自分の思考が冷静さを欠いていると感じたら、結論を急ぐよりも段階的に考えを進めるのが有効です。
まず、あなたがしたいのは「退職」ですか?それとも「転職」ですか?
動機または目的が、「退職したい」なのか「転職したい」なのかは、転職したい企業または業界が決まっているかによって分けることができるはずです。
転職希望先の有無と動機・やるべきこと
| 転職したい企業または業界 | 主な動機 | やるべきこと |
|---|---|---|
| ①決まっていない | 転職したいというより退職したい | 緊急性あり ⇒心身の不調は医師などに相談 自分を守ることを最優先する 緊急性なし ⇒期限をつけてできることをやってみる できることの例 ・自分の強みの棚卸 ・転職のメリット・デメリット分析 ・勤務先との待遇交渉や転属願 ・転職したい企業や業界の洗い出し ・将来性など市場分析 |
| ②決まっている(内定はまだ) | 転職したい | ・転職のメリット・デメリット分析 ・転職希望先の情報収集 ⇒分析・情報収集の結果により転職活動を開始 |
| ③すでに内定を得ている | 転職したい | ・改めて分析+情報収集 ・引き止めにあった場合の対応を考えておく ⇒最終決断+引継ぎ |
今回記事のテーマは、いったん「転職の決断ができない心理」であり、転職ノウハウの詳細ではありません。
ですが、自分が上の表中のどの状態にあるかを把握するのは意義があるはずです。
「合理性」だけでは心は測れない
- 現在の職場の問題点について整理
- 自分の棚卸し
- 転職のメリット・デメリット分析
これらを既に実施済みの方もいるかと思います。
それでも転職(あるいは退職)が決断できない、というのは前述のように人間の心の中には「バイアス」がいくつもあり、分析や論理による「合理的な答え」だけでは自分自身を納得させることができないからです。
そこで次に、「視点を変えてみる」にトライしてみます。
自己分析②:視点の変化で分かること
近年で注目を浴びる「コーチング」(または「ビジネスコーチング」)においては、コーチは相談者に正解を与えるのではなく、質問を繰り返すことによって気づきをもたらす、という手法をとります。
中でも良く行われるのが「視点を変えてみることをうながす」タイプの質問です。
例えば…
- もし、自分と同じ状況の友人がいたら、どのようなアドバイスをしますか?
- 5年前のあなたが現状を見たら、どう思いますか?
- 5年後のあなたが現状を見たら、どう思いますか?
- 時間や手間など、制約が何もなかったとしたら、どんな選択肢が考えられますか?
- あなたの尊敬する人なら、この問題にどうアプローチするでしょうか?
転職について自分の問題として考えると、現状維持バイアスや損失回避バイアスの影響で、リスクばかりが大きく見えるかもしれません。ですが自分がアドバイスする側に立って俯瞰した途端、問題は思ったよりもシンプルで、すぐに転職活動を始めるべきだ、という結論に至る可能性もあります。
この方法は、思考の堂々巡りで疲れてしまった方におすすめです。
参考までにコーチングとコンサルティングその他の相談技法の違いについて簡潔にまとめてみました。
コーチングとその他の技法の比較
| 項目 | コーチング | ティーチング | コンサルティング | カウンセリング |
| 主な目的 | 目標達成・成長の支援 | 知識やスキルの伝達 | 専門知識による課題解決 | 心の問題や悩みの解決 |
| アプローチ | 対話で気づきを引き出す | 指導者が一方的に教える | 専門家が解決策を提案 | 話を聴きながら問題の本質を探る |
| 主体 | 相談者(自分で答えを見つける) | 指導者(教える側が主導) | コンサルタント(専門家が主導) | クライアントとカウンセラー(共同で探る) |
| 扱うテーマ | 未来志向・目標・行動 | 正解がある知識や技術 | 業務課題・経営課題など | 過去の悩みや心理的な問題 |
| 期間の目安 | 比較的長期 | 短期~中期 | 短期~中期 | 比較的長期 |
他人の力を借りて、問題を客観視してみる
もちろん実際にコーチングを受けてみるのも有効です。
ただし繰り返しになりますが、コーチは質問によって気づきのきっかけ与えるのであって、正解を教えてくれる存在ではない、という点に注意が必要です。
また、プロのコーチ以外にも、有効な相談相手として以下の人が考えられます。
- 転職希望の企業または業界に在籍する知人
- キャリアコンサルタント
- 転職エージェント
- 家族やパートナー、友人
これらの人に相談することで、自分では見えていなかった視点を得られたり、「自分は、自分で思っていたより頑張っていたんだ」と気づけることもあります。ただし、あなたとの関係性やコーチなどの肩書に関わらず、あなたの話を聞くよりも自分の考えを押し付けてくる人への相談はやめておくべきでしょう。

最も相談相手にふさわしくない人の例
話をろくに聞かずに「俺の方がもっと苦労した。今の若いやつは甘えている」的な話を始める人。
なお家族やパートナーは、あなたの転職により生活に影響を受ける立場でもあるので、場合によっては相談を控えた方が良いこともあります。
行動編①:まず始めてみることでやる気が出る
やる気が出ないという受験生の悩みに対して、
「まずはとにかく始めることが重要で、やる気はその後で追い付いてくる」
といったアドバイスを読んだことはないでしょうか?
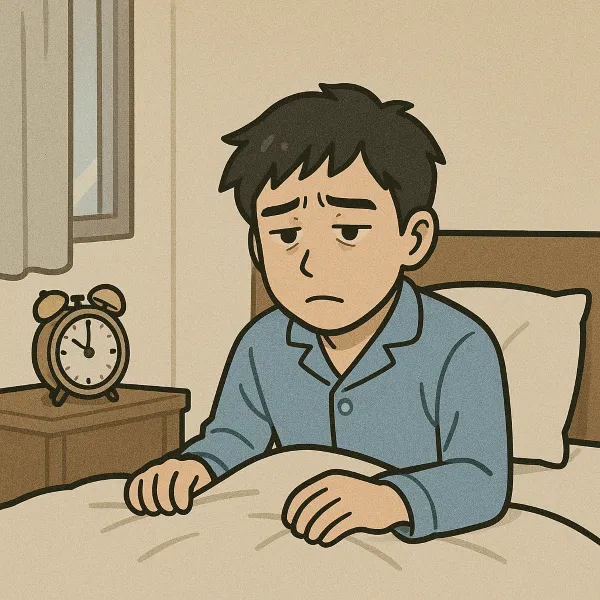
モチベーションが低下した人の朝
起きるのもツラいという人に向かって
「とにかく、まず始めろ」
というのは酷な気もしますが、心のメカニズムのうえでは理にかなっています。
一見、これは随分と適当なアドバイスに思えてしまいますが、実は「作業興奮」または「作業興奮効果」という心理効果に基づいています。作業を開始することで興奮状態になり、集中力ややる気が高まるというメカニズムによるものです。
似たような考え方に自己知覚理論(Self-perception theory)というものがあり、これもやはり行動を起こすことで「自分が行動している=自分はやる気があるのだ」と自ら認知することで、やる気が後からついてくるという考え方です。
先に挙げたバイアスもそうですが、人の心の中にはおよそ合理的とは言えない、
「なんでそんな変な仕組みがあるんだ!」
と、思えるようなものがいくつもあります。そういったメカニズムについて学んでおくことで、自分の心と上手に付き合っていけるかもしれません。
転職活動は人生の少なくとも一部がかかった重要な案件です。
だからこそ「面倒くさい」という気持ちが湧いてくる前に、
- まずは自分の得意な業務を簡単にまとめてみる
- 興味のある業界について調べてみる
- 転職エージェントに登録だけしてみる
- 各エージェントの無料相談を活用、自分の適性や市場価値を診断してみる
など、ハードルが低そうなことから始めることで「やる気のスイッチ」を上手く入れてあげるべきではないでしょうか?
【転職を検討中の方におすすめの記事】
行動編②:慎重な情報収集でミスマッチを防ぐ
しっかりとした情報収集は転職の成否を分けるポイントです。
現在は転職サイトに加えてSNS、YouTube、など多彩な情報源が存在しますので、入社後のミスマッチを防ぐために、できるだけの情報収集を行うべきです。
• 求人情報を定期的にチェックする
• 転職サイトで気になる企業の社員の声をチェック
• 転職系YouTuberやブロガーの経験談を参考にする
• 転職エージェントの無料カウンセリングを受ける
これらを活用することで、「今の職場と比べてどうか?」だけではなく、「長く働き続けるのにふさわしい職場か」といった視点が持てるようになります。
退職者から得られた情報で「企業のリアル」を知る
さらに、昨今では気になっている企業について、実際に退職した人の「本音」を知ることで、転職後に後悔する可能性を減らすことも可能です。
転職したい企業のリアルを知るには?
退職代行サービス「モームリ」で有名な株式会社アルバトロスでは、本当の退職理由・労働環境など、退職者から得た情報を知ることができるサービス『MOMURI+(モームリプラス)』を提供しています。
※下記リンクをクリックすると外部サイトに遷移します。
退職代行を利用した方が残した情報が、あなたの転職を成功させるカギとなるかもしれません。
まとめ|「その気になれば転職できる」という安心感
ここまで転職にまつわる心理について解説してきましたが、この記事の目的は、必ずしも転職に迷っている方の背中を、無理に押すことではありません。
それよりも、転職活動を始めたことで
転職エージェント経由で、面接のオファーが〇件もあった!
自分には市場価値があるんだ!
ということを知ることの方が、転職するかどうかよりも意味があるかもしれません。
特にパワハラ気味の上司により自信を失いかけている、といった状況にある方にとっては心が楽になるのではないでしょうか?
結論:
- 転職活動をしたからといって実際に転職しないといけない訳ではない
- むしろ転職活動の過程での、自己分析や自信回復にこそ意味がある
- 転職しなかったとしても「自分はその気になれば転職できる」という自信は今後の支えになる
そういう意味では、転職活動は自分を見つめ直す好機になるはずです。
なお、転職したい理由が上司の圧迫的な態度にある方は、以下の記事も参考にしてください。

よくある質問&疑問(FAQ)
本記事を最後までご覧頂き、誠にありがとうございます。
内容に関して、想定される疑問点およびその対処法についてFAQ形式でまとめました。




コメント