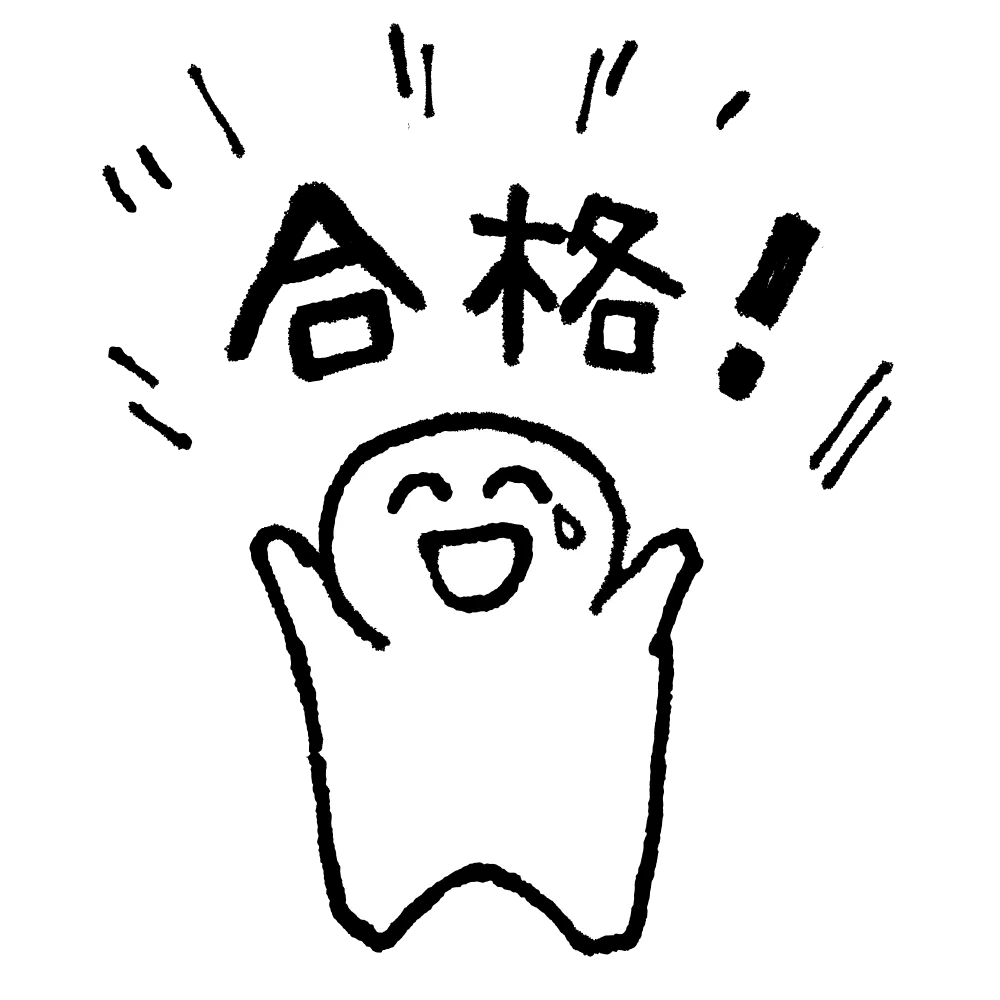※本ページにはアフィリエイト広告が含まれています。
何か新しいことを始めるのに
「やった方がいいことは分かっているのに、始めるのが面倒くさい」
ということってありますよね。

あぁ…
ちょー面倒くさいんですけど
そして、あれこれ考えているうちに時間ばかりが過ぎてゆき、

あの時、アレを始めていれば、きっと自分は今ごろ…
…みたいな感じになります。
ということで、今回は私自身へのメッセージも込めて「やる気・モチベーションの維持対策」について、まとめてみました。
よくある議論:成功に必要なのは努力?才能?
実績のあるアスリートの発言で
「自分には才能が無いから、他人の何倍も努力するんだ」
みたいなのをインタビュー記事で読んだことがある方は多いのではないでしょうか?

一方で「努力ができることも才能のうち」という、若干冷めた言い方をする人もいます。
私はこれらの見方とは少し違って「努力をするのには(才能というよりも)自信が必要なのでは」みたいなことを昔から考えていました。
これは例えるなら、宝くじを買う人・買わない人の心理に似ていると思います。
宝くじを買うのは「もしかしたら当たるかも」と思うから
人が宝くじを買うのは「もしかしたら当たるかも」と、期待しているからです。反対に「絶対に当たるわけない」と考えている人は、何か特殊な事情でも無い限り買わないはずです。
この考え方を当てはめると、努力できる、特に他人の何倍もの努力を継続できる、という人は
「自分は努力したらきっと目標を達成できる!少なくとも達成できる可能性は大いにある!!」
と、考えているはずです。つまり自信を持っているわけです。
反対に「自分ならできる」と思っていないのに努力できる人は、「宝くじなんか絶対当たるわけない」と思っているのに買っている人みたいなもので、やってることに辻褄が合いません。もっとも、あえて自分を苦しめるのが好き等、特殊な嗜好をお持ちの方は当てはまりませんが…
上に書いた心境を、もう少し違う表現にしてみると、
「自分には、人並みの練習量で人並み以上の成果を出せるような能力、いわゆる『才能』は無いけど、人並み以上努力をすればきっとイケるはず!」
こんな感じになると思います。
冷静に考えると、スポーツや芸能などの分野では努力しても必ず報われるとは限りません。むしろ努力しても成功できない確率の方がずっと高いはずです。それでも「自分ならやれる」と、特に根拠も無いのに思えることは、競争の激しい分野で生き残るうえで才能と同等以上に重要な要素なのかもしれません。
心のメカニズムを行動経済学の視点から考えてみる
残念ながら「実績を上げるために他人の何倍も努力してやる!」と決意し、実行できるのは少数派です。
そこまでの強固な自信と意志を持たない、我々一般人が努力を続けるためには、まず心のメカニズムを知る必要があります。
行動経済学の視点①:期待値
先ほどの宝くじの例でいくと、人は何らかのポジティブな結果が期待できるから、すなわち「期待値」があるからコスト(時間、労力、お金)をかけてでも行動を起こす、という見方ができます。
つまり、自信がある人は「目標の達成」という期待値を持っているからこそ、努力ができるわけです。
行動経済学の視点②:損失回避バイアス
人間が、得をする喜びよりも損失による心の痛みの方をより大きく感じる、という傾向を損失回避バイアスと呼びます。
損失回避バイアスは、例えば以下のような形で努力しようと思っている人の前に立ちふさがります。
あなたは「今度こそ絶対成功させる!」という決意とともに、ダイエットを始めました。
ところが人気ラーメン店の前を通りがかると、あなたはフラフラとお店に入ってしまいました。
ラーメンがダイエットの敵であると分かっていても、ついつい食べてしまう心理的なメカニズムはなんでしょうか?
①ダイエットの成功は、将来得ることができるかどうか不確かな利得
②目の前にある人気ラーメン店で美味しいラーメンを食べるのは、確実に得られる利得
このため、
①のために②を失うことは、損失回避バイアスにより心理的な抵抗が発生する。
個人差はあるかと思いますが、人の心の中ではこういう困った心のメカニズムが働いています。
そのため努力により得られるはずの期待値は、目先の快楽(例:飲み会に行くこと、休日に1日中YouTubeを視聴しながらダラダラ過ごすこと、など)にあっさりと負けてしまいがちです。
損失回避バイアスは生存に役立つ?
損失回避バイアスは人の努力を邪魔をする場合もある、困った心のメカニズムです。
ですが、これが悪いものとは言い切れません。
大昔の狩猟時代:目前に迫った危険の回避や、その日の食料確保が最優先
現代社会:受験勉強、キャリア形成など長期的・計画的な努力が重要
ということで、読者の皆さんや私の祖先が生き延びることができたのは、こういった損失回避バイアスのおかげである可能性もあります。ただ、社会の変化に対して心のメカニズムが追い付いていない点が問題です。
それでも努力を継続するには?
ここまで書いたように、人は
努力して得られそうなもの(期待値) > 必要なコスト(労力・時間など)
こう感じられなければ、やる気が出ないようになっています。
そこで損失回避バイアスを乗り越え、努力を続けるためには、
期待は大きく、コストは小さく、
そう感じられるように自分を誘導する必要があります。
期待を大きく:目標の具体化と達成イメージの明確化
ダイエットでの例:
単に「痩せる」ではなく、「〇月までに〇kg減量し、好きな服を格好良く着こなす自分」のように、目標を五感で感じられるほど具体的にイメージする。その達成がもたらすポジティブな感情や状況(健康、自信など)を強く意識し、ワクワク感を高める。
コストを小さく:ハードルを下げて、自分を「その気」にさせる
達成が難しいと感じる目標でも、小さな要素に分解することで「自分にできる」という確信を持ちやすくなる。
資格取得での例:
簿記、英語、法律系の資格など、いきなり難関資格に挑むのではなく、難易度の低いものから攻略する。
少しでも勉強が進んだら「今日は忙しかったけど5問解いた!」など成果を言語化する(口に出す、ノートに書きつける、など)
努力しない場合の「損失の大きさ」を自分に刷り込む
再びダイエットでの例:
ダイエットをサボれば「健康」「自信」「理想の体型」といった貴重なものを失う。目先の快楽が長期的な損失に繋がることを繰り返しイメージする。
継続 VS 効率の追求
資格取得を目指している方が、ネット記事や動画の一覧の中に「効率が上がる特別な勉強法」みたいなのを見つけると、ついつい気を取られてしまいます。
一方で、努力を続けることさえできれば、そのうち自分なりの効率的なやり方に辿り着ける可能性が大です。そのため最初から効率を追求するよりも、まずは続けられるように自分のモチベーションを管理することが重要です。
「そもそも始められないんですけど」という困った悩み
ここまでは「努力が続けられないんですけど」という悩みについてですが、それ以前に「スタートできない」という、より困った悩みが存在します。
自己知覚論
心理学者のダリル・ベムが提唱した理論で、私たちは自分の行動を観察することで、自分の態度や感情を推測するというものです。
部屋の掃除の例
最初は嫌々でも、やり始めて部屋がきれいになるのが実感できると、きりがつくまでやり遂げたくなる。
何かの勉強で「1問だけでも解こう」と始めたところ、いつのまにか何時間も勉強していた、といって経験がある方は多いと思います。
これは脳が「あれ?自分は勉強しているな。ということは、勉強したいのかもしれない」のように、行動に対してモチベーションがついてくる仕組みを備えているからです。
つまり、
とにかく、どんなに小さくてもいいから一歩を踏み出す
ということが重要です。
認知的不協和と「気持ち悪さ」
「認知的不協和」などと用語を出すと大げさな感じがしますが、人間は自分の行動に矛盾があると内心で気持ち悪さを感じる、ということです。
資格取得の例
先に高額の通信講座を申し込み、料金を払ってしまう。そうすると勉強しない自分にいら立ちが募ってくるのでスタートできる。
まとめ:大事なのは、自分を嫌いにならないこと
損失回避バイアスのところで説明したように、人間の心はそもそも長期的な努力を優先するような仕組みになっていません。
また、努力をスタートしないとモチベーションが上がらない、といった困った仕組みも備えています。
つまり、未来のために何らかの努力を始め、そして継続していくことは、人の心のメカニズムに逆らうことだ、という側面があります。
だからこそ、あなたがもし「努力が続かない」「すぐに諦めてしまう」と感じても、自分を責めるのはやめましょう。それは、あなたの意思が弱いからでも才能がないからでもなく、人間という生物の自然な特性だからです。
こうした人の心の特性を理解し「完璧には程遠くても、とにかく一歩でも前に進む」ことに集中できれば、いつか目標達成につながるかもしれません。