※本ページにはアフィリエイト広告が含まれています。
あなたの職場に、こんな人はいませんか?
「自分はできる」
「あの人より自分の方が優れている」
本人はそう信じて疑わないのに、実際の成果や振る舞いが伴っていない。

自己評価が高すぎる人は、一見すると自信に満ちていて頼もしく見えることもあります。しかし、その「過剰な自信」が周囲との関係にズレや軋轢を生みやすく、チーム全体のパフォーマンスや雰囲気に悪影響を与えることがあります。
しかも厄介なことに、その相手が「上司」だった場合。あるいは「部下」や「同僚」だったとしても、自己評価が現実と乖離していると、指導も協力も難しくなりがちです。
今回の記事では、自己評価が高すぎる人の心の中が一体どうなっているかを考えつつ、彼らが職場にもたらす影響と、それぞれの立場(上司・部下・同僚)別に「どう付き合い、どう自分を守るか」という実践的なヒントをお届けします。
※本記事は、ビジネス・日常生活における一般的な場面についての内容です。専門的な診断や治療が必要な場合は医療機関への受診ををおすすめします。
自己評価とは何か?自己肯定感・自己効力感との違い
本題について進める前に、「自己評価」と混同しやすい概念について整理しておきます。
そもそも自己評価とは?
「自己評価」とは、自分の能力や価値に対する認知のことを指します。
つまり仕事や人間関係において、
「自分はどの程度役に立っているか」
「どれだけスキルがあるか」
を自分自身で判断する感覚です。
この評価は必ずしも現実と一致するとは限りません。自分を過大評価してしまう人もいれば、逆に過小評価してしまう人もいます。
ここでは「高すぎる自己評価」に焦点を当てていますが、それが問題になるのは、実力との乖離が大きくなったときです。
自己評価が実力に対して…
高すぎる人が言いそうなセリフ
「私に任せれば、こんな簡単なことはすぐ片付きますよ。」
「私の指示通りにやらないから上手くいかないんですよ。」
低すぎる人が言いそうなセリフ
「私より、もっと適任な人がいるはずです。」
「私が皆さんのお役に立てているか、不安です。」
自己評価と自己肯定感との違い
「自己評価」と混同されがちなのが「自己肯定感」です。
これは、自分の存在そのものに価値があると感じる心の状態です。つまり、「ありのままの自分に価値がある」と思える感覚であり、成果や能力に依存しないものです。
自己評価が高くても、自己肯定感が低い人は多く存在します。外側に強さを装いながら、内面では常に他者からの評価に怯えている状態です。これが、「自信満々なのに、なぜか不安定に見える」人の心理的な背景にあることもあります。
自己評価が高くて自己肯定感も高い人が言いそうなセリフ
他人に業績に対して:「素晴らしいアイデアですね!きっと成功しますよ。」
自分の業績に対して:「失敗は残念ですが、ここから学んで次はもっと良い結果を出します。」
⇒自分のことを肯定的に捉えているので、他人に対して否定的にならず、自分の失敗に対しても前向き。
自己評価が高いが自己肯定感は低い人が言いそうなセリフ
「もっと完璧にできたはずなのに。私はなんてダメなんだ…。」
⇒「成果を出した自分」しか認められないので、上手くいかないと自己を否定してしまう。
自己評価と自己効力感との違い
もうひとつ混同されがちなのが「自己効力感」。これは目標や課題に対して「自分ならなんとかできる」と信じる感覚のことです。
自己効力感は、自己評価の一部に含まれることもありますが、より行動志向的です。
自信過剰な人の中には、この自己効力感が過剰になりすぎ、根拠のない「万能感」を持ってしまうケースがあります。現実的な困難を軽視し、過信により失敗を繰り返すこともあります。
自己評価・自己効力感とも過剰な人が言いそうなセリフ
「彼が失敗したのは、やり方が悪かったからだ。私ならもっと短期間で完璧に仕上げてみせます。」
自己評価は高いが自己効力感は低い人が言いそうなセリフ
「もっと良い環境なら、私の実力を発揮できるはずなんだが、この職場では無理だろうな。」
総じて、自己評価が高すぎる人は
「自分の優位性を常に確認したい」
「他人が自分より優れていることを認めたくない」
といった感情が強く働く為、他人に対して否定的で、いわゆる「マウントをとる発言」をしがちです。また他人からの批判を自分への攻撃として捉えてしまうので、素直に受け入れることが難しくなります。

すぐにマウントを取りたがる同僚にウンザリしている人
ということで、実力に見合った自己評価、自己肯定感、自己効力感を持つことが、本人にとっても周囲にとっても理想的な状態であると言って間違いなさそうです。
自己効力感/自己肯定感/自己評価 比較表
| 比較項目 | 自己効力感 | 自己肯定感 | 自己評価 |
| 対象 | 特定の課題・行動 | 自分の存在全体 | 自分の能力 |
| 関連性 | 「できるかどうか」の感覚 | 「価値があるかどうか」の感覚 | 他者との優劣の比較 |
| 基づくもの | 経験・スキル・周囲の評価 | 自己受容・内面的な信念 | 自己内の基準 |
| 役割 | モチベーション・挑戦への意欲 | 回復力・精神的安定 | 自尊心を保つ |
自己肯定感および自己効力感について、以下の記事にてさらに詳しく解説しています。

「自己評価が高すぎる人」の心理的背景とは?
次に「自己評価が高すぎる人」の心の中がどうなっているのかについて深掘りしていきます。
ダニング=クルーガー効果とは
この現象を語る上で外せないのが、ダニング=クルーガー効果(Dunning-Kruger Effect)です。これは、能力の低い人ほど自分の実力を過大評価してしまうという認知バイアスの一種です。
能力が不足していると、自分の欠点や他者の優秀さを適切に認識する力にも欠けているため、「自分はできる人」と錯覚しやすくなります。一方で、能力の高い人ほど自分の限界をよく理解しており、「自分はまだまだだ」と謙虚に考えがちです。
職場では、こうした錯覚が
「自分はもっと評価されるべき」
「あの人より自分の方が適任だ」
という誤認に繋がりやすく、コミュニケーションや信頼関係に亀裂を生じさせます。
自己認知のズレがもたらす影響
自己評価が高すぎる人は、しばしば「なぜ自分が評価されないのか」に納得がいかず、組織の評価制度や上司を批判する傾向があります。しかし、それは客観的に見れば「自己認知」がズレてしまっていることに問題があります。
たとえば、実際の業績やスキル、周囲からのフィードバックと本人の自己評価が大きく乖離している場合、本人は「不当に扱われている」と感じがちです。これは確証バイアス(自分の信じたい情報だけを信じる傾向)とも関連し、他人のアドバイスを受け入れにくくしてしまいます。
このズレが放置されると、パフォーマンスにも悪影響が出るばかりか、職場のチームワークや信頼関係にも悪影響を及ぼしかねません。
「自信過剰」と「無意識の不安」の関係性
興味深いことに、過剰な自己評価の裏には「自己肯定感の低さ」や「無意識の不安」が潜んでいることがあります。
一見、堂々と自信満々に見える人が、実は自分の価値を信じておらず、他者からの評価や失敗を極度に恐れている…。そんなケースも少なくありません。
これは、心理学的には「防衛的自己評価」と呼ばれるもので、自分を守るために必要以上に“できる自分”を演出している状態です。周囲からの称賛を求め、評価が得られないと極端に落ち込んだり、攻撃的になったりする傾向があります。
自分を大きく、優れた人間としてアピールしないと不安という意味では、自分を強く見せようとしている10代の若者と基本的に同じ心理だと言えます。
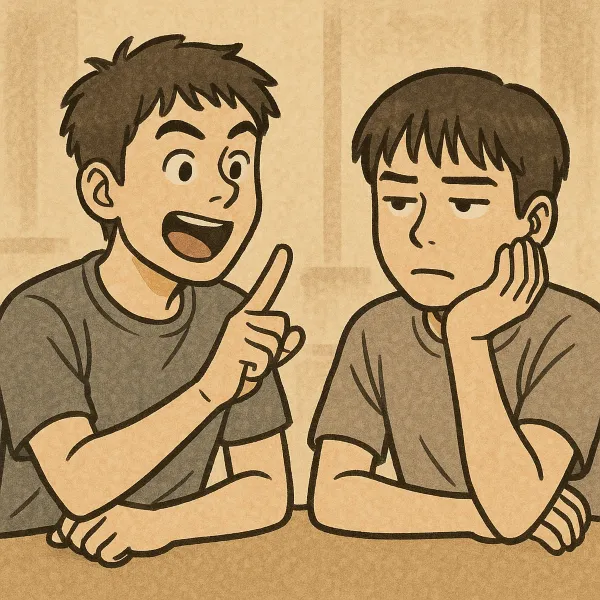
すぐに武勇伝を語りたがる友達にウンザリしている少年
つまり、表面的な「自信過剰」には、繊細で弱い心の防衛反応が隠されていることが往々にあります。
自己評価が高すぎる人との付き合い方:上司編
ここからは自己評価が高すぎる人との付き合い方です。
まず上司が過剰な自己評価を持っている場合、部下としては非常に厄介です。自分の判断が常に正しいと信じているため、
- 他者の意見を受け入れない
- 評価の基準が自己中心的になる
など、マネジメント上の問題が生じがちです。
このような上司のもとでは、部下は萎縮しやすく、建設的なフィードバックや提案がしづらくなります。また、結果としてチームの士気が低下し、職場全体のパフォーマンスにも影響します。
「ナイーブ・リアリズム」への理解
「ナイーブ・リアリズム」とは、自分の見解こそが現実を正しく反映しているという思い込みです。自己評価が高い上司は、まさにこのバイアスにとらわれていることが多く、「自分が見えている世界こそが正しい」と信じています。
このタイプの上司に対しては、
「このようなアンケート結果が出ています」
「官公庁による統計はこちらです」
といった、客観性を意識した提示の仕方を心がけることが重要です。
このタイプの上司は自尊心を傷つけられたと感じると攻撃的な反応を返してきます。別の視点もあることを慎重に伝えることが、健全な関係を維持する鍵となります。
「Iメッセージ」で刺激を避けて伝える
さらに自己評価の高い上司との関係で疲弊しないためには、「I(アイ)メッセージ」による伝達もポイントです。
たとえば、
「あなたの意見はバランスを欠いています」
という言い方だと絶対評価のような印象を与えてしまうので
「私にはあなたの意見がバランスを欠いているように思えます」
といった自分を主語にした意見(Iメッセージ)を使い、あくまで個人の感想を伝えているだけのようなスタンスを取ることで、相手を刺激せずに意見を伝えることができます。
また、無理にすべてを伝える必要は無く、
「あの人はこのままだと失敗するかもしれないけど、私がそれに責任を感じる必要は無い」
といった線引きを明確にすることも重要です。
他の選択肢を示して、相手に選んでもらう
感情的にぶつかってしまうと、自己評価が高い上司は防衛的・攻撃的になりやすく、さらに状況が悪化します。そのため、論理と事実に基づいた冷静な伝え方が求められます。
たとえば、「その方法では難しいかもしれませんが、こういうアプローチなら可能性があります」といった、選択を委ねる形でのコミュニケーションが効果的な場合が有ります。
相手は自分に主導権があると思うことで支配欲が満たされるので、議論の余地を残せるかもしれません。
また、必要以上に評価を求めず、「自分の目標に集中する」視点を持つことが、ストレス軽減にもつながります。
自己評価が高すぎる人との付き合い方:部下編
部下が自己評価が高すぎるタイプだった場合、
「指示を素直に聞かない」
「自分流にやりたがる」
「失敗しても責任を取ろうとしない」
などの問題が発生しやすくなります。
こうした部下には、曖昧な表現ではなく、具体的な行動・結果に基づくフィードバックが重要です。また、過信を戒めるような「叱責」よりも、現実的なデータや比較によって自覚を促す方が効果的な場合もあります。
期待値の再設定と目標管理
過剰な自信を持つ部下には、明確な期待値の提示が不可欠です。「このレベルを達成すれば合格」という基準を明文化することで、本人の思い込みをリセットできます。
これにはSMART目標、すなわち
- Specific:具体的な目標を設定すること
- Measurable:達成度合いを測定可能な指標で測ること
⇒悪い例「顧客満足を向上させる」
⇒良い例「顧客アンケートで、”良い”または”大変良い”の解答率を80%以上にする - Achievable:現実的に達成可能な目標を設定する
- Relevant:関連性がある
⇒例:営業部の目標を、全社の事業計画など上位目標とリンクしたものにする - Time-bound:期限が明確である
そのうえで定期的な進捗確認と振り返りの場を持つことで、自信過剰になることを抑えられます。
適切なフィードバックの重要性
評価が高すぎる部下には、やんわりと否定ではなく、具体的かつ行動ベースのフィードバックが必要です。
たとえば、「プレゼンの内容が素晴らしかった」と漠然と褒めるのではなく、「事例の使い方が分かりやすく、特に〇〇の説明が効果的でした」と具体的に伝えると、本人の成長実感にもつながります。
同様に、改善点についても「この部分は改善の余地があります。具体的には〜」と事実に基づいて指摘することで、防衛的反応を最小限に抑えられます。あくまで「矯正」ではなく「育成」の視点が重要です。
自己評価が高すぎる人との付き合い方:同僚編
ここでの同僚とは、同じ職場で上司・部下の関係にない人を指します。
同僚が過剰な自己評価を持っていると、チームでの協力が難しくなります。自分の意見が常に正しいと信じているため、話し合いが成立しない、他人の功績を自分のものにする、協調性を欠いた言動を取る…といったトラブルが起こりがちです。
このような場合は、感情的な対立を避けながら、一定の距離感と戦略的無関心を保つことも必要です。
自分のメンタルを守るためにも、
「相手を変える」
のではなく、
「自分の関わり方を変える」
という考え方が重要です。
感情の境界線を引く方法
同僚が自己評価の高いタイプで、しかも仕事に支障をきたすほど協調性に欠けている場合、精神的なストレスが積み重なってしまいがちです。そうしたときに大切なのが、「感情的境界線」を引くことです。
これは、「自分の感情と他人の感情を分けて考える」というスキルで、シンプルに言えば「人は人、自分は自分」という考え方です。
相手の態度や発言が不快でも、それに過剰に反応しないためには、
「これはあの人の課題」
「自分は冷静に役割を果たす」
と一歩引いて見る視点が必要です。
心の中で線を引くことで、自分の精神的なスペースを守ることができ、過剰に消耗することを防げます。
正論ではなく「関係性」の戦略を持つ
自己評価が高すぎる人との関係では、「正論」だけでは物事が前に進まないことが多いです。いくら筋が通っていても、相手がその正論を受け入れるとは限らないからです。
このような相手には「話せば分かる」と、どちらの意見が正しいかを論じるのはいったんあきらめて、
「ほめて動かす」
「巻き込む」
などにより、自分の意図する方向に誘導する方が有効な場合があります。
決して迎合する要はありませんが、対立を避けつつ目標を達成する、という視点を持つことで、働きやすさが格段に変わります。
限界を感じたら専門家への相談という選択肢も
どうしても関係が改善せず、自分の成長やメンタルヘルスに悪影響が出ている場合は、専門家への相談やキャリアチェンジも一つの選択肢です。
「自分が悪いのかもしれない」と一人で抱え込むのは危険です。実際、自己評価が高すぎる人が周囲に与えるストレスは非常に大きく、キャリアの停滞やバーンアウト(燃え尽き症候群)にもつながりかねません。
また、自分では対処できないと感じた場合や、仕事や日常生活に支障を感じた場合は、専門家に相談することも検討すべきです。
※以下のリンクをクリックすると外部サイトに遷移します。
あなたの周りにもいる?:「自己評価が高すぎる人」タイプ別の対応策
ここまでは上司や部下といった立場ごとに、自己評価が高すぎる人への対処法をご紹介しました。
それとは別にタイプごとにアプローチを変えみるという考え方も有ります。
ここでは試みとして
1.孤高の絶対王者タイプ
2.承認欲求モンスタータイプ
3.未完の天才(評論家)タイプ
4.繊細な鎧(よろい)武者タイプ
以上4つのタイプの特徴を確認しつつ、それぞれのタイプに合わせた具体的な対応策を解説します。
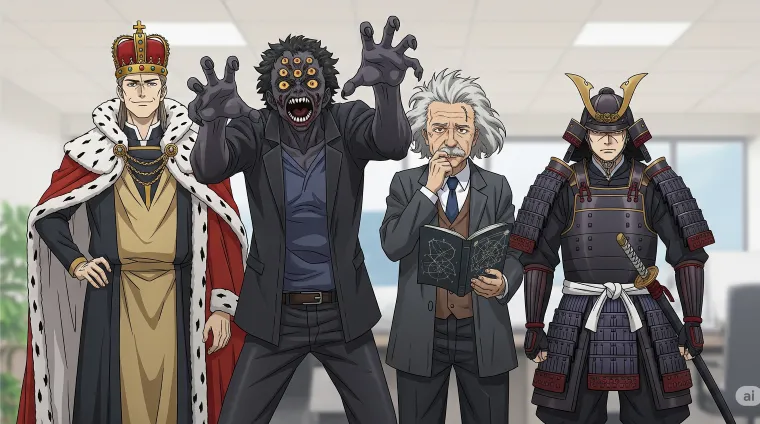
「自己評価が高すぎる人」4タイプ
絶対王者(王様)、モンスター、天才、鎧武者のイメージです。
1.孤高の絶対王者タイプ
特徴: 自分の能力が常に最高だと信じて疑わず、他者の意見や助言には耳を傾けません。自分のやり方こそが唯一の正解であり、失敗は他者や環境のせいだと考えがちです。
言いそうなセリフ:
「こんな簡単なこともできないのか?俺がやった方が早いな。」
「私の案が最も優れている。議論の余地はない。」
ありがちなエピソード:
プロジェクトの進捗会議で、メンバーが問題点を指摘しても、
「私の指示通りにやれば問題ない」と一蹴。
最終的にプロジェクトが難航しても、自分の責任だとは微塵も思わず、
「君たちの能力が低いせいだ」と公言。
孤高の絶対王者タイプへの効果的な対応策
- 「事実」と「数字」で冷静に伝える: 感情論ではなく、客観的なデータや具体的な数字を用いて状況や課題を提示します。「〜というデータが出ています」「〇〇の目標に対し、現状は△△です」のように、反論しにくい事実を突きつけます。
- 「選択肢の提示」で主導権を持たせる: 指示や命令ではなく、「A案とB案がありますが、どちらが良いとお考えですか?」のように、彼らに選択の余地を与え、主導権を握っていると感じさせることで、反発を和らげます。
- 「最終的な成果」への影響を指摘する: 彼らのプライドを傷つけないよう、「あなたの能力を最大限に活かすためにも、この点を改善すれば最終的な成果がさらに高まります」といったように、彼ら自身のメリットに繋がる形で改善を促します。
このタイプは部下の立場からの対応策が必要になる場面が多いかと思います。
①②は対上司向け、③は部下や同僚向けの対応策です。
2.承認欲求モンスタータイプ
高い自己評価の一方で、心の奥底に
「認められたい」
「褒められたい」
という強い承認欲求があるタイプ。
常に注目を集めようとし、自分の手柄を誇張したり、他者の功績を軽視したりします。
言いそうなセリフ:
「今回の成功は、私の指揮があってこそのものだ」
「あのアイデア、実は私が〇〇さんにヒントをあげて形になったんだよ。」
ありがちなエピソード:
チームで達成した目標について、上司への報告時には自分の貢献度を実際よりも大きくアピール。他のメンバーが陰で地道な作業をしていたことを知っていても、あたかも自分が全てを指揮したかのように語り、賞賛を独り占めしようとする。
承認欲求モンスタータイプへの効果的な対応策
- 具体的に「承認」を与える: 彼らの良い点や貢献に対しては、具体的に「〇〇の点で助かった」「あなたの△△の行動がチームに貢献した」と、明確に承認の言葉を伝えます。ただし、過剰な褒め言葉は逆効果になることもあるため、事実に基づいた承認を心がけます。
- 手柄の分配を明確にする: チームでの成果については、各メンバーの貢献度を具体的に示し、手柄の分配を明確にすることで、彼らが独り占めしようとするのを防ぎます。
- 建設的な「役割」を与える: 承認欲求を満たすため、彼らがリーダーシップを発揮できるような具体的な役割や責任(例:「〇〇の進捗管理を任せたい」「新人の指導をお願いしたい」)を与えることで、健全な方向へエネルギーを向けさせます。
主に、このタイプが部下になってしまった場合の対処法です。
3.未完の天才(評論家)タイプ
理論や知識は豊富で、自分には計り知れない才能があると信じていますが、実際に行動に移すことや、具体的な成果を出すことには及び腰です。他者の行動や成果に対しては批判的で、上から目線でアドバイスしたがります。
言いそうなセリフ:
「そのやり方ではダメだ。こうすべきだ。」
「私はいつか大きな仕事をやる。今の職場は単なる踏み台でしかない。」
ありがちなエピソード:
同僚が企画書作成で悩んでいると
「ああ、私は以前、似たような企画を立案したことがあるから詳しいよ」
など、具体的な手助けはしないのに持論を展開。いざ自分に企画書作成のタスクが回ってくると、なかなか着手せず、場合によっては多忙を口実にして他の人に押し付ける。
未完の天才(評論家)タイプへの効果的な対応策
- 「アウトプット」を求める視点を明確に: 批評や理論だけでなく、「では、それを具体的にどう実現しますか?」「次のステップとして、何から着手しますか?」と、具体的な行動やアウトプットを促します。
- 「行動へのハードルを下げる」手助け: 完璧主義ゆえに行動できない場合があるので、スモールステップでのタスク分割を提案したり、「まずはたたき台で良いので」と、完璧でなくても良いことを伝えたりして、行動へのハードルを下げます。
- 「知識の活用」を促す機会提供: 彼らの豊富な知識を活かせる場(例:情報共有会での発表、新人へのレクチャー)を設けることで、評論家としての立場だけでなく、実践的な貢献の機会を与えます。
こちらも主に、このタイプが部下になってしまった場合の対処法です。「チーム内の評論家」で終わらせず、結果に対して責任を持たせるようにしましょう。
4.繊細な鎧(よろい)武者タイプ
外向きには自信満々で自己評価が高く見えますが、その内面には「失敗したくない」「完璧でなければならない」という強い不安や弱さが隠れているタイプです。一見して自信満々に見える姿は、傷つきやすい自分を守るための「鎧」のようなものです。
言いそうなセリフ:
「私にできないはずがない。ただ、今回は準備期間が短すぎる。」
「彼らは頭が悪すぎる。私の提案を理解できないのも仕方ない。」
ありがちなエピソード:
新しいシステム導入の担当になった際、「私がやれば大丈夫です!」と豪語し、周りの意見をあまり聞かずに突き進む。しかし、裏では些細なミスも許せず、夜遅くまで一人で資料を何度も見直すなど過剰な準備を行う。いざ不具合が発生すると、感情的になり、自分の非を認めることを強く拒否する。
繊細な鎧武者タイプへの効果的な対応策
- 「安心できる場」と「共感」を提供する: 彼らの発言の裏にある不安やプレッシャーに寄り添い、「大変でしたね」「無理しないでくださいね」といった共感の言葉をかけ、安心して弱みを見せられるような関係性を築くことを意識します。
- 「完璧でなくて良い」ことを伝える: 期待値を調整し、「完璧を目指さなくて大丈夫」「〇〇までできれば十分」といった言葉で、彼らの過剰なプレッシャーを和らげます。
- 「小さな成功」を丁寧に承認する: 小さな成果でも見逃さずに具体的に褒め、「よくやったね」と声をかけることで、内面の不安を軽減し、自己肯定感を高めるサポートをします。
自信満々に見える態度の裏側に不安や繊細さが隠れていることを踏まえて、心理的なハードルを下げるような伝え方がポイントです。
【重要なお願い】
これらのタイプ別の対処法は、あくまで一般的な指針です。
目の前の相手の個性を尊重し、柔軟な姿勢でコミュニケーションを取ることが何よりも重要です。
身近な人の「自己評価が高すぎるタイプ」判定チェックリスト
このチェックリストは、あなたの身近な人の言動を観察し、どのタイプに当てはまる傾向があるかを考えるための参考としてごご活用ください。
【重要なお願い】
このチェックリストは、あくまで類型的な傾向を把握するためのものであり、特定の人物を診断したり、安易に決めつけたりするためのものではありません。人の心は複雑であり、様々な要因によって言動は変化します。この結果を元に、決めつけやレッテル貼りをすることは避け、相手を理解し、より良い関係性を築くための一助として慎重にご利用ください。
以下の質問に「はい」「いいえ」「どちらとも言えない」で回答してください。(クリックで開きます)
- 自分の意見が常に正しいと強く主張し、他者の反論を受け入れない傾向がある。
- チームやプロジェクトの成功を、ほとんど自分の手柄だと語ることが多い。
- 他者の成果や貢献を、あまり認めようとしない、または軽視する発言が多い。
- 自分の能力や実績について、実際の成果以上に語ることがよくある。
- 失敗や問題が起きた際に、自分以外の原因(人や環境)を指摘することが多い。
- 「自分は特別な存在だ」「普通の人とは違う」といった意識が垣間見えることがある。
- 新しい仕事や役割を任せると、「自分なら楽勝だ」といった自信過剰な発言が多い。
- 人の話を聞くよりも、自分が話すことに強い関心があるように見える。
- 完璧でないことや、少しのミスでも、過度に自分を責めるような発言をすることがある。
- 他者に対して、上から目線で一方的にアドバイスや批評をすることが多い。
- 知識や理論は豊富だが、実際に困難な課題に取り組むことにはためらいが見られる。
- 自分の弱みや不安を見せることを極端に嫌がる傾向がある。
- 周囲からの注目や称賛を強く求め、それが得られないと不機嫌になることがある。
- 自分の能力を認めない人がいると、その人を露骨に批判したり、軽蔑したりする。
- 些細なことでも、自分の行動や判断の正しさを必要以上にアピールする。
- 他者の意見を聞く際も、自分の意見を通すための材料集めのように見えることがある。
- 周囲が心配するような無謀な計画や行動を、自信満々で推進しようとすることがある。
- 「もっと評価されるべき」「自分の居場所はここではない」といった不満を漏らすことがある。
- 自分の感情をあまり表に出さず、常に強い自分でいようとする。
- 周囲が困っている時でも、具体的な手助けよりも、口頭での指示や批評に終始しがち。
察しの良い方はすでに気づいているかと思いますが、これら4タイプは完全に独立したものではなく、複合的に表れる場合があります。繰り返しになりますが、あくまで目安とお考え下さい。
判定の目安はこちら(クリックで開きます)
あくまで目安ですが、それぞれのタイプの傾向が強い質問項目に多く「はい」と答えた場合、そのタイプの特徴が強く出ている可能性があります。
- 孤高の絶対王者タイプ:
⇒ 1, 3, 5, 6, 7, 14, 17, 20 に「はい」が多い - 承認欲求モンスタータイプ:
⇒2, 4, 8, 13, 15 に「はい」が多い - 未完の天才(評論家)タイプ:
⇒ 10, 11, 18, 20 に「はい」が多い - 繊細な鎧武者タイプ:
⇒9, 12, 16, 19 に「はい」が多い
このチェックリストが、あなたやあなたの身近な人との関係性を考える上で、少しでもお役に立てれば幸いです。
健全な自己評価を育み、自分を活かす方法
自己評価が高すぎても低すぎても、ビジネスや私生活において様々な課題が生じます。最も理想的なのは、自分の実力に見合った自己評価、そしてそれを支える健全な自己肯定感と自己効力感を持つことです。
どのようにすれば、私たちはよりバランスの取れた自己評価を育み、前向きに毎日を送れるようになるのか、そのための具体的なステップと実践的な習慣をご紹介します。
事実ベースで自分の強み・弱みを把握する
まずは感情的なフィルターを通さず、客観的なデータや具体的な行動に基づいて、自分の能力や成果を評価しましょう。
- 「今週の売上は目標に5%届かなかった」といった具体的な数字で成果を見る
- 「あのプロジェクトでは、〇〇の知識が不足していた」といった明確な弱点を認識する
- 「Aというタスクを〇〇分で完了できた」といった具体的な行動を記録する
「できる」と信じること(自己効力感)は行動の原動力になりますが、それが根拠のない思い込みになると逆効果です。
重要なのは、自己評価が現実に見合っているかを確認し続ける習慣です。数値的な成果の振り返りの他に、上司や同僚からの定期的なフィードバックなどを通じて、自己認知の精度を高める努力を忘れないようにしましょう。
「成長」に焦点を当て、小さな成功体験を積み重ねる
自己評価が低い人は、完璧を求めすぎて行動できない傾向があり、逆に高すぎる人は、自分の現状に満足しすぎて成長を怠ることがあります。
「成長」と「小さな成功」に焦点を当てることで、健全な自己評価を獲得できます。
スモールステップで目標を設定する
「今週中に、〇〇の資料作成を完了させる」
「毎日10分、新しいプログラミング言語の学習をする」
大きな目標をいきなり目指すのではなく、手の届く範囲の小さな目標を設定し、それを一つずつクリアしていく喜びを実感することが大切です。
なお、今回記事とは反対に「自己評価が低い人」については、こちらの記事をご覧ください。

また、自己を客観視するのに役立つ「メタ認知」については、こちらの記事をご覧ください。
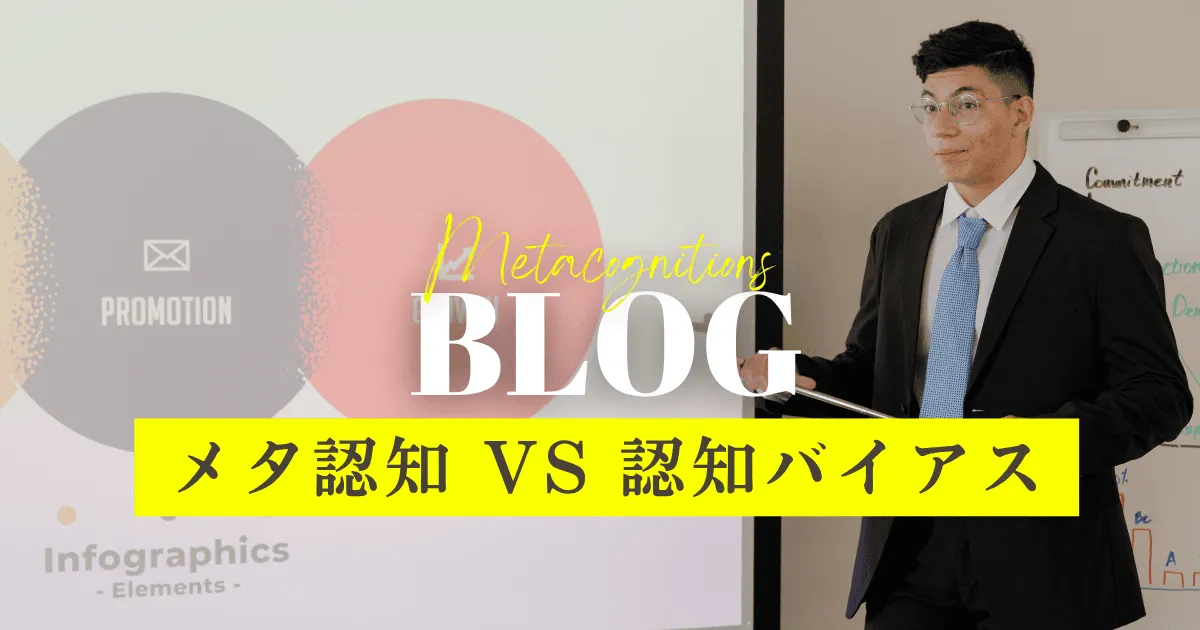
まとめ|関係を壊さずに自分を守るために
「自己評価が高すぎる人」は、職場においてしばしばストレスの原因となりますが、彼らを「排除すべき敵」と見なすのではなく、心理的メカニズムを理解し、適切な対応をとることが、あなた自身のキャリアと心を守る最善の道です。
本記事では、自己評価・自己肯定感・自己効力感の違いから始まり、行動経済学的な背景、上司・部下・同僚それぞれの立場での対処法、さらには自分を守るメンタルスキルまで解説してきました。
「このままでいいのか?」と迷ったときは、自分だけで抱え込まず、第三者の力を借りることも選択肢に入れてみてください。無料のキャリア相談や心理学講座など、行動のきっかけはすぐそばにあります。
この記事の主旨は必ずしも転職をすすめることではありませんが、転職の決断については以下の記事もご覧ください。
【転職を検討中の方におすすめの記事】
よくある質問&疑問(FAQ)
本記事を最後までご覧頂き、誠にありがとうございます。
内容に関して、想定される疑問点およびその対処法についてFAQ形式でまとめました。


